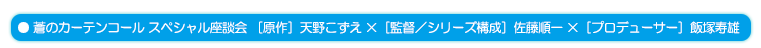◆ARIAシリーズを振り返って 前編
――TVアニメがスタートした10年前のことを振り返っていただけますか?
飯塚 あの頃って『ARIA』のように、何か事件が起こったり敵が出てきたりしない中でドラマを紡いでいく作品は少なかったですよね。
天野 まったくないわけではなかったんですけど、たしかに多くはなかったです。
飯塚 とくにアニメの世界では、余計にそうだったと思います。ですからアニメ化の企画書を作ったときも、過去の参考例がなくて困りました。「これからはこんなアニメが求められるはずです」と訴えてみるものの、上司からは「いつ戦いがあるの?」などと聞かれたりもして(笑)。
佐藤 でも、そんな作品がしっかりと反響を得て、シリーズ化されたってことは、やはり需要があったんでしょうね。
飯塚 前例があまりない作品だったので、放映が始まった頃はどんな反応が帰ってくるのか、不安がないわけではありませんでした。当時はツイッターのようなファンの反応を可視化してくれるメディアがなくて、放送中の盛り上がりを計るものがなかったんです。おかげで周囲の好意的な反応を感じつつも、うかつに喜べない状態で。DVD第1巻の反応が非常に好評だったので、ようやく確かな手応えを感じることができました。それと、終盤の11話(『その オレンジの日々を…』)が放映されたあとの盛り上がりは、今でも鮮烈に覚えています。
天野 11話はコンテの段階から素晴らしかったですね。歌を入れてくるタイミングが絶妙すぎて、これぞ佐藤監督の真骨頂!という感じでした。
飯塚 いい原作をいいアニメにする、お手本みたいな1本ですよね。
佐藤 1期のときは13本できれいに終わらせることになっていたので、どうまとめるかでけっこう悩んだんですよ。考えていたのは、適度にオリジナル要素を挟みつつ、主人公の灯里にアクアでの居場所がちゃんと用意されるまでを描くことでした。翻って作品を観る人がどんなふうに受け取るかを考えたときに、例えば田舎から上京して新しい生活に馴染んでいくように、身の回りの環境が次第に自分のものになっていく過程に共感してもらえたらいいなと。一応、設定は未来なんですけど、それが作品の中でダイレクトに機能していないのもすごくいいスパイスになってますよね。未来なのに郵便屋さんが手紙を配達していたり。
天野 『ARIA』という作品では、幸せを描くことがコンセプトでした。何か事件が起きてそれを解決するまでを描くような作品のまとめ方に限界を感じていたこともあって、一度その枠を取っ払って自由に遊んでみたいと思ったんです。その上で、誰かに向けてというより、まずは自分が好きものを徹底して描いてみようと。でも、連載が始まったときは「この作りで何話まで持つのか?」とよく言われました(笑)。
佐藤 幸せのストックにも限界がありますからね。
天野 幸せだけだとさすがに難しかったですね。マイナスな感情を描きながらも、それをプラスの言葉でまとめるのがポイントなんです。ですから、プラスに変換するアイデアさえ思いつけば、あとは何でもありだったりするんですよ。
飯塚 2期で晃さんが悪口を言われる話(24話『その 明日のウンディーネに…』)は、まさにマイナスをプラスに変換する作りでしたよね。やりようによっては暗い話になってしまいそうですが、最後にちゃんと前向きな流れに持っていくのがすごいと思いました。
天野 すべての人が納得できる答えではないかもしれませんが、私なりにプラスに捉えられる言葉をきちんと提示することを心がけてきました。そのあとはもう、自分はもちろん、客観的な視点を持った編集さんにも納得してもらった上で描いていますから、きっと読者にも納得してくださる方がいるはず!と信じるしかない(笑)。
佐藤 結局のところ、受け取る人の心の持ちよう次第というところもありますからね。でも、考え方のヒントはたくさん詰まっていると思いますよ。みんな自分の考え方を切り替えるスイッチをそう多く持っているわけじゃないんですけど、それをふと目の前に提示してくれるような感じ。「そうそう、それが欲しかったやつ」みたいな(笑)。
飯塚 僕がこの作品で感心したことのひとつに、ライバル店を闇雲に増やさなかったことがあるんです。ネタのストックが尽きてくると新しいライバルを次々と登場させがちですが、それがないんですよね。
天野 まずテーマとして訴えたいことがあって、それを描くために必要なキャラクターを配していく作り方をしているので、増やす必要がないんです。それに最小限のキャラクターでいろんなエピソードを積み重ねたほうが、個々のキャラクターへの愛着もわくと思いますし。あとは単純な処理能力の問題ですね。あまり広げすぎると、自分でもよくわかんなくなっちゃうんですよ(笑)。
佐藤 そこはやっぱり好きであることの強みですよね。好きなものだけを愚直に描くことが作品のパワーにつながっているというか。マイナスのことをプラスに変換して描くというのも、話としては理解できますけど、いざやれと言われてもそう簡単にはできませんから。
――天野先生は、ご自身の作品がアニメ化されたことで何か影響はありましたか?
天野 キャラクターがアニメになって動くのを観たときに、初めて自分の作品を客観視できるようになりました。自分の内から出てきたキャラクターではあるのですが、どこか友だちのことを見るような感覚で捉えられたと言いますか。そのおかげで、原作のキャラクターも以前とは違った動き方をするようになったんです。元々それなりに動いてはいたのですが、それ以上に勝手に動き出しちゃって(笑)。先日、連載を終えてから初めて作品を読み返す機会があったのですが、ちょうどアニメが始まった6巻の辺りからキャラクターの動き方が目に見えて変わっているのがわかってびっくりしました。『ARIA』がこれだけ多くの人に支持していただける作品になったのは、アニメ化の影響がすごく大きかったのだと、あらためて感じました。
飯塚 アニメから原作への目に見えたフィードバックと言えば、アイちゃんの存在が極めつけですね。アニメオリジナルの要素が、原作においてあそこまでインパクトのある形で生かされるというのは、あまり例のないことだと思います。1期をやっていた頃は、まさか原作にまで登場するなんて想像もできませんでした。
天野 アニメ化の恩恵をとても強く感じていたので、原作とアニメで仲よく一緒にゴールインできたら素敵だなと思いまして。最終話の構想が浮かんだときから後輩を出すことは決めていたのですが、当初は顔を出すつもりはなかったんです。でも、よくよく考えてみたら、アイちゃんがいるじゃん!みたいな(笑)。
佐藤 そもそも最初から『ARIA』を1年4クールの作品としてやると決まっていたら、アイちゃんは出ていなかったはずなんですよ。13本でまとめるときに灯里のナレーションが誰に向けたものかわからないまま描くのは難しいと思い、アニメオリジナルのキャラクターを設定させてもらった経緯がありますので。なんだか素敵な奇跡ですね(笑)。
[後編につづく] |